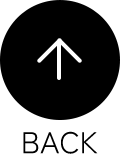要望を形にするだけでは足りない
プラスαの付加価値で
「想像以上」の空間に

O:
デザイン設計部 デザイングループ
2023年 中途入社
※2025年対談時の所属と役職になります
Y:
デザイン設計部 デザイングループ
グループリーダー
2018年 中途入社
※2025年対談時の所属と役職になります
Y:
私たちデザイン部は、コンペ案件にしても受注案件にしても、これからつくる空間を最初に見える形にする部署ですよね。Oさんはどんな部分を心がけていますか?
O:
お客さまの意図に沿っているかはもちろん、意匠の美しさや機能性、動線なども当然考えますが、そこにプラスαで付加価値をつけて「プロジェクトが楽しくなるような期待感」を提供したいですね。関わる人がワクワクしてつくることが良い結果へと導いてくれると思っています。
Y:
その「付加価値」を導き出すことが大切ですよね。これがあるとお客さまが求める結果にもっと貢献できる何か、を提案に加えていくことで「想像以上によかったよ」「ありがとう」と喜んでもらえる。そのためには、プランニング能力やデザインスキルとともに、コミュニケーション能力をつけていくことが求められますね。これは空間づくりのどの工程にも言えることです。
O:
そうですね。前に飲食店のプレゼンテーションで失注してしまったときは、自分のコミュニケーション能力の未熟さを痛感しました。「絶対取りたい!」と細部までつくり込みをして自分なりに納得できた提案だったのですが、実際に選ばれたのは私がヒアリングしてきたものとはまったく雰囲気の違うものでした。大事な情報を聞き逃したかもしれないし、自分の思い込みもあったかもしれないと、自分自身に悔しさを覚えた経験でした。
お客さまのほうでイメージがしっかり固まっていないときもあれば、ちゃんとしたイメージがあっても、そのことを過不足なく伝えるには説明が難しい部分もありますよね。そこを自分なりのイメージで受け取るのではなく、コミュニケーションのなかで明確にしていかなきゃいけないんだなと学んだ経験でした。
そのときは一旦気持ちをリセットするため、1週間ほど休暇をいただき、次に向けてリフレッシュいたしました(笑)。
Y:
コンペは多いときには5社くらい競合会社があるし、どの会社も自分たちで考え抜いたものを提案してくるので、取れなかったこと=自分たちの力不足というわけではないけれど、ではなぜ取れなかったか、どこに不足があったかの振り返りは大事ですよね。そうやってもなお「自分たちの提案のほうがよかったよね」というときもあるし(笑)。成長のきっかけにして、次の仕事つなげられればOKです。
人に寄り添うデザイン・設計で
心地よく、記憶に残る空間に


O:
Yさんにとって「良い提案」「良い空間」とはどんなものですか?
Y:
案件によっていろんな制約があるので、それをクリアしたうえで「意匠性やグレード感が合っているか」は気にしています。また、利用者にとって心地よく、記憶に残る空間であってほしいので、「人に寄り添うデザイン・設計になっているか」という部分は特に意識していますね。たとえば、その空間に椅子とテーブルがあるとすると、「そこでどんなことが生まれるか」など使われ方まで具体的にイメージして、形や材質、サイズ、触感や使用感まで「なぜこれを選んだのか」を明確に答えられるくらいまで詰めて考えます。
O:
想像力を広げていくことでディテールが決まっていくんですね。加えて、アイデアのストックも必要で、それが付加価値の提案につながっていくのだと思います。でもアイデアって机の前で唸っていても出てきませんよね。Yさんはそのために普段から意識していることはありますか?
Y:
みんなやっていることではありますが、新しいスポットや話題の場所には必ず行くようにしていますね。今はインターネットで情報を入手できますが、やはり実際に足を運んで感じたことをインプットするようにしています。
O:
情報収能力って大事ですよね。そうして提案するときは、仕入れた情報を整理する能力も大事かもしれません。私の場合、アイデアは話しながらじゃないと出てこないので、とにかく人とよく話すようにして仕入れた情報を共有したり、意見を言い合ったり。そうするといろんな視点があることに気づきます。
また、特定の提案についてアイデアを練るときはリサーチをしっかりします。たとえばその案件が商業施設なら市場調査をするのは当然ですし、ノムラアークスと長くおつきあいのあるお客さまであれば、これまでどんな案件を受けてきたかをチェックします。そうすると、方向性や期待値が把握できますし、付加価値の積み上げ方なども見えてきます。そうして情報を整理しておけば、最初の設計通りにいかないときも方法を見つけやすいと思います。
Y:
そうですね。空間づくりのプロセスでは提案通りにいかない場面がよくあります。さらに「そこを変えるなら、ここも変更しなければ」というようにことも多々あるので、そんなときに決して方向がぶれない、品質を落とさない代替案をサッと出せるように、情報を整理しておくことはとても重要ですね。


アイデアと発想力、対応力を育てて
多角的なアプローチで課題に向かう
Y:
自分の仕事における「クリエイティビティ」について、どのように捉えていますか?
O:
一言で表すならば、「斬新なアイデアと発想力」です。これまで話したことと重複するのですが、やはり課題があるときや問題が起きたときに、「ではこういう案はどうですか?」と別の切り口をたくさん出せる人がクリエイティブな人だと思います。ただ、一朝一夕にできることではないので、今私にできることは、場数を踏んで地道に培っていくということなんでしょうね。
Y:
アイデアや発想力は確かに経験によって育てられますが、今、そこにプラスして「クリエイティビティ」に特化した講習や勉強会を企画しています。忙しいなかでも受講できるオンライン講座や外部講習なども予定しているので、楽しみにしていてください。そして、リラックスして自分を遊ばせる時間も必要だと思うので、仕事ばかりを詰めずに存分に楽しんでください。
O:
ありがとうございます。Yさんにとっての「クリエイティビティ」もぜひ教えてください。
Y:
私もOさんと同じで、課題に対して「多角的にアプローチし、付加価値を生み出す力」かな。予算、納期、意匠性、機能性、安全性、耐久性など、意識すべきポイントは多岐にわたります。加えて、今は持続可能性や省エネ性、環境配慮といったSDGsの視点も欠かせません。もちろん法規をクリアすることも必須です。柔軟性と対応力を身につけてこそ、多角的なアプローチが可能になると考えています。
グループの一人ひとりが自分のクリエイティビティを大切に育てて、「選ばれるデザイングループ」でありたいですね。
O:
頑張ります!